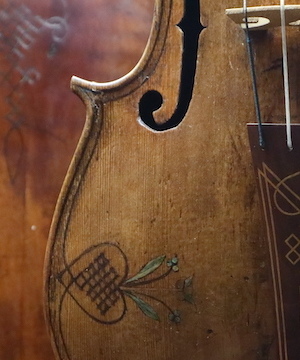■日曜・月曜定休
Closed on Sundays & Mondays
10:30~18:30
112-0002 東京都文京区小石川2-2-13 1F
1F 2-2-13 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 JAPAN
後楽園駅
丸の内線【4b出口】 南北線【8番出口】
KORAKUEN Station (M22, N11)
春日駅 三田線・大江戸線【6番出口】
KASUGA Station (E07)
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form
- 毛替え予約(PC & 携帯より)Reservation for Rehairing

ワンランク上の演奏レコーディング術
魅力ある演奏動画を作るためには、音や映像の高いクオリティが欠かせません。……というと敷居が高く感じますが、実は普段使っているスマートフォンを正しく使ったり、家庭でも比較的取り入れやすい外付けマイクなどの機材を活用したりすることで、音や映像の質をぐっと向上させることができます。
ドイツでトーンマイスターの資格を取得し、ご自身でも演奏活動を行っている録音・録画のプロである金井哲郎さんに、スマートフォンなどを使って演奏を録音・録画するときの注意点を教えてもらいました。
主なポイントを6つ挙げ、見ていきましょう。

音と映像をワンランクアップさせるための工夫
まず最初に、録音する場所を選ぶところから始まります。1.余計な音を入れないこと
自宅で録音するときにまず気をつけるべきは、生活音です。録音を始める前に、周りの音に耳を澄ませてみましょう。「基本的には、自分に聞こえる音は全て録音されると思ってください。小さい音だから大丈夫かな、というものも大抵全て録音されます。工事、車、救急車などのサイレン、冷蔵庫や隣室のテレビの音、パソコンのファンノイズなどにも気を付けてください」
2.(なるべく)良い響きがする部屋で録ること
次に、録音する場所を選びます。どのような音の響きになるのか、録音する前に視覚的に確認できるポイントもあります。「とにかく響けばいいというものでもありません。大事なのは演奏される曲に相応しい響きかどうかです。
基本的には物が多い部屋は残響が少なくなり、物が少ない部屋は残響が多くなります。また、堅い平らな壁が並行にある場合は、その間で演奏してしまうと特定の周波数が強調されてしまうので、なるべく避けてください。
あとは、自分が心地よく演奏できるかということも大事です。あまりに残響が無さすぎる部屋だとそもそも演奏がしにくいですが、弾きやすい(または弾きなれた)部屋で演奏して後から電気的な残響を足しても良いと思います」
3.音楽録音用のマイクを正しく使うこと
マイクを買い足せる場合には、いろいろな選択肢があります。家庭でも比較的取り入れやすい機材にはどのようなものがあるのでしょうか。「スマートフォンに外付けのマイクを繋ぐと音質を飛躍的に向上させることができます。また、1万円程度(例えばZOOM H1n等)の音楽録音用マイク付き小型レコーダーも初心者には良い選択肢です。
もっと凝った録音をしたい場合はXLR入力の付いたマイクプリアンプ付きレコーダーと、2本のマイクを用いて録音してみてください。この場合、単一指向性マイクも悪くないのですが、無指向性マイクを使うとより自然なステレオ感を表現できます」
マイクを正しく使うことも大切です。
「中には音楽録音に適さないものもあります。特に、インタビューなどに使われるショットガンマイクではマイクの向きから少し外れてしまうだけで全く違う音になってしまうため、音楽録音には通常使いません。
また、サイドアドレス型のマイクを間違った向きで使ってしまうことはよく初心者が犯しやすい間違いですので注意してください」
4.マイクを置く位置に留意
「マイクを置く位置もとても大事です。①なるべくスタンドを用いてください。机の上などに置くと余計な反射音が入って音が変わってしまいます。
②基本的には楽器から良い音がする (たくさんの倍音が聞こえる)ところに設置すればいいと思ってください。大雑把に言えば、ヴァイオリン・ヴィオラなら楽器より高く、表板側に設置します。チェロ・コントラバスは楽器の正面側なら割合どこでも大丈夫です。木管楽器は楽器によって様々ですが、基本的にはベルなどではなく楽器の中央部付近に向けます。金管楽器はベル付近にマイクを向けるほどはっきりした音が入りますが、直接的過ぎる音にもなりやすいです。その場合は楽器やマイクの向きをずらして調整してください。
これらはあくまでも基本的な位置でここから大きく外れることはありませんが、少し場所を変えるだけで録音される音は変わります。
③楽器とマイクの距離に気をつけてください。使うマイクや部屋や楽器によって変わるのではっきり何メートルとは言えませんが、およそ1~3メートルくらい離してマイクを置いてください。
また、アンサンブルの場合は、それぞれの楽器の音のバランスが良くなる場所を探してください。同じ音量の楽器から等距離離れると同じ音量に録音されますので、ピアノ伴奏付きソロの場合はソロ楽器や歌手の前にマイクがあれば、ソロが大きくなり伴奏が若干小さめになります(曲や楽器や部屋などにも依りますので絶対ではないです)。これらを逆手に取ると、小さい音量の楽器は近くにして、大きい音量の楽器を少し離して録音してバランスを取ることもできます。
④録画に適したカメラの位置と、録音に適したマイクの位置は全く違うということに注意してください。カメラとマイクは別々に設置し、それぞれを適切な位置に置けるようにすると良い結果を得やすくなります」

5.トライアンドエラー
テンポの速い曲とゆっくりした曲をそれぞれ弾いて聞き比べてみると、マイクの位置による音の変化が分かりやすいそうです。「あるメロディを数十秒録音してからマイクや奏者の位置を変え、同じメロディをもう一度録音して聞き比べると、音の変化が良く分かります。テンポの遅い曲には適切な響きでも、早いパッセージには合わないということもあるので、それぞれを少しずつ録音して聞き比べることを繰り返すと良いでしょう」
6.必要に応じて電気的な補正をかけること
録音し終わった演奏をクリアに聞かせたり、より磨きをかけたりするために、音楽制作ソフトを使って補正することもできます。「クラシック音楽でよく使う電気的な補正はイコライザー/フィルターとリバーブです。特にローカットフィルターは状況に応じて使ってください。例えば440Hzのヴァイオリンの最低音は約196Hz、ヴィオラは131Hz、チェロは65Hz、コントラバスは41Hzです。これ以下をカットすることで、外を走る車の音を低減したりすることができます。他にも、リバーブと呼ばれる電気的な残響を付加することで音は大きく変化します。
これらの処理を行うにあたって、自分の使っているスピーカーやイヤホンが基準のものではないことを念頭に置いておいてください。極端な例では、自分のヘッドホンで良い音に聞こえても、他のヘッドホンやスピーカーでは全然違う風に聞こえてしまうこともあります。こういった問題を避けるためには、音楽制作向けのヘッドホン・スピーカーを使うことが一つの手段です。ドイツのトーンマイスターの間ではSTAXやSennheiserのヘッドホンがよく使われています。これからスピーカーを購入する方はモニタースピーカーとして販売されているモデルから選ぶことをお勧めします。ただし、スピーカーは再生する部屋の残響の影響を非常に強く受けてしまいますので、注意してください。
また、ヘッドホンとスピーカーでも聴取時の印象は大きく変化しますので、両方で聴いて確認することが大事です」

録画をするときのポイント
動画として制作する場合には、音だけではなく映像のクオリティも大きな要素です。特に弦楽器奏者が演奏する映像を録るとき、少しでも見やすく魅力的な動画にするために工夫できることについて伺いました。
「大事なのは、自分が見せたい部分がどこなのかをよく考えて撮影することです。そして、その見せたい部分が全部映っているかに注意してカメラを設置してください。
例えば、ヴァイオリンではE線を弾いた時が一番大きく上下に弓が動きますので、弓まで全部映そうと思ったらE線を弾いた状態で確認する必要があります。また、『(弓ではなく)ヴァイオリンと顔が映ること』を基準にすると、左手の動きと演奏者の表情をより良く伝えられます。意図があってのことなら、顔のアップや指のアップ等でももちろん構いません。
複数のカメラで同時に録画し後から編集する手法も、表現の可能性を大きく広げてくれます。その場合は同じメーカーや同じ機種で揃えると色を合わせやすいです」
上記のポイントをふまえて機材をうまく使えば、ぐっと音質、映像の質が良い動画を作ることができるのではないでしょうか。是非、ワンランク上の演奏動画や録音づくりに挑戦してみてくださいね。
取材・文/安田真子