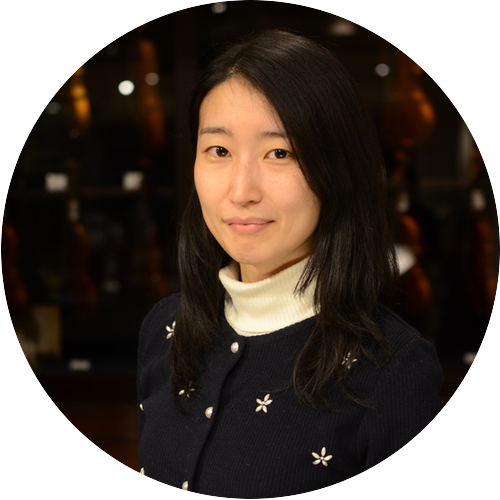■日曜・月曜定休
Closed on Sundays & Mondays
10:30~18:30
112-0002 東京都文京区小石川2-2-13 1F
1F 2-2-13 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 JAPAN
後楽園駅
丸の内線【4b出口】 南北線【8番出口】
KORAKUEN Station (M22, N11)
春日駅 三田線・大江戸線【6番出口】
KASUGA Station (E07)
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form
- 毛替え予約(PC & 携帯より)Reservation for Rehairing

新しいバロック音楽のフェスティバル『Baroque at the Edge』 in London
現代には、ヴィオラ・ダ・ガンバやリュートなどの古楽器をあえて音響機器に接続したり、本来のレパートリーとは異なる音楽に挑戦したり、バロック音楽の作品を現代的なアレンジを加えて演奏したりと、通常考えられていたこととは異なるアプローチで演奏に取り組む音楽家たちがいます。
バロック音楽を題材に自由な感性で作り出されていく新しい音楽は、古楽器の演奏を愛する人だけではなく、ポップスやロックを聞く人にとっても親和性があり、刺激的です。そのような通常とは一味違う演奏が繰り広げられるバロック音楽祭『Baroque at the Edge』が、イギリス・ロンドンで1月10日から12日までの週末3日間にかけて開かれました。
バロック音楽を題材に自由な感性で作り出されていく新しい音楽は、古楽器の演奏を愛する人だけではなく、ポップスやロックを聞く人にとっても親和性があり、刺激的です。そのような通常とは一味違う演奏が繰り広げられるバロック音楽祭『Baroque at the Edge』が、イギリス・ロンドンで1月10日から12日までの週末3日間にかけて開かれました。

- エレクトリックのヴィオラ・ダ・ガンバ二重奏
雪でも降りそうな1月の寒い夜。21時半を回った頃、イギリス・ロンドンにあるホールLSO St.Luke'sには続々と人が集まってきました。幕が開くと、舞台上にはヴィオラ・ダ・ガンバを奏でる2人の女性が現れました。その前方にはもう1台、テールピース部分が折れ、弦が外れた状態の壊れた楽器が横たえられています。
舞台照明はジャズやブルースなどのライブのような色合いで、ときに赤く、ときに青く演奏者たちを照らし出し、二重奏は通常のヴィオラ・ダ・ガンバという楽器から想像されるものとは異なる音色を響かせています。楽器を音響機器にあえて繋いでいることは一つの大きな違いですが、今までに耳にしたことがないほど野性的で生き生きとしたガンバの音色に圧倒されました。
このドイツの母娘デュオ、ヒレ・パール、マルト・パールによるヴィオラ・ダ・ガンバの二重奏には神秘的な響きがあり、複雑に絡み合う演奏には音楽の力強さで満ちていました。いつもはテールピースから音響機器に繋げられる特製のエレキ・ガンバを携えてデュオ活動をしているこの2人。コンサートの前々日に母ヒレの楽器が突然壊れてしまったので、代わりの楽器で演奏したけれど、壊れたままの愛器も舞台に一緒に乗せたかったと曲の合間にヒレは語りました。
「この楽器の修理はできるけれど、アンコールとして『葬送曲』を贈ります」と演奏者本人の口から微笑みをもって伝えられると、聴衆から忍び笑いが漏れ聞こえてきました。
前置きなしに伝わる音楽
BBCのラジオで音楽番組のプロデューサーを長年務め、ロンドンでのバロック音楽祭の芸術監督の経験もあるリンシー・ケンプ(Lindsay Kemp)さんが、自らの経験をふまえて独自のフェスティバルを作りたいと願ったことがきっかけでBaroque at the Edgeという音楽祭は生まれました。同音楽祭では、音楽の歴史的な価値や位置づけ、どう聞くべきかという曲目解説の書かれたプログラムノートは配られません。レクチャーも無し。目指すものは、ポップスやジャズ、ワールドミュージックのようなジャンルのライブのように、「ただ聞くということ」だけで伝わる音楽なのだとケンプさんは語ります。
2018年に同音楽祭が始まってから、バロック音楽を取り巻く状況はどのように変わったのでしょうか。
「1970年代に『アーリー・ミュージック・ムーヴメント』がヨーロッパで起きてから、バロック時代の忘れられていたレパートリーの発掘のみならず、当時の音楽家が使っていた楽器と奏法といった多くの発見がもたらされました。現代の趣向やリソースに200、300年前の音楽を適合させるのではなく、オリジナル楽器を見つけ出して使用し、先祖たちの解釈のスタイルを再創造するために扱い方を学んだのです。そこで彼らが作り出した音は示唆的で魅惑で、さらに奏法や音色、バロック音楽を取り巻く環境についてより深い理解のもと、これらのレパートリーについての私たちの考えは良い方向に変化していきました。
多くは演奏が難しいそれらの楽器を弾く演奏家のスキルが上がるにつれ、バロック音楽の演奏法はより直感的になり、素晴らしいバロックの即興能力が花開き、演奏表現の自由と自立を得ました。だからこそ、今は『現代のバロック音楽演奏家の兄弟分には最もエキサイティングな音楽家たちが含まれている』と言うべきだと私は思います。
同時に、クラシック音楽の楽器の『通常の』、『モダンの』演奏者や、ジャズやワールドミュージック、インプロヴィゼーションや現代音楽など、よりフリースタイルの音楽ジャンルのプレイヤーもこの素晴らしいバロック音楽の創造の世界に惹きつけられてきました。
『オーセンティックな』『歴史的解釈』『ピリオド奏法』といった演奏方法には、生まれながらの抑制が長きにわたって伴っていました。いかにエキサイティングなパフォーマンスをしていても一種の歴史的な文脈に身を置く傾向があり、説明的な曲目解説や学習のためのレッスンという感覚があり、コンサートは半分が娯楽で半分が歴史の授業であるかのようです。さらに、この歴史的アプローチからの逸脱は、音楽的な成果に依らず、未だに詫びるべきものか『罪深い楽しみ』として言い逃れをするべきもののように見えます。こういった制約から外れようとするのがこの音楽祭なのです。あらゆる領域から来てバロック音楽を演奏したり、バロック音楽を素材として新しい表現方法を模索し、生き物のように扱うことを選んだアーティストたちの才気を私は讃えたいのです」

- 若手奏者も個性的なプロジェクトで活躍
土曜の午前中に小さな教会で開かれた若手ヴァイオリン奏者のマヤ・カディッシュの午前中のコンサートでは、バロックとモダンヴァイオリンを持ち替えるほか、一つの主題からヴァリエーションを発展させ、ミキサーを操って自分の演奏に更に演奏を重ねていく手法で、チプリアーノ・デ・ローレの『Ancor che col partire』、クラウディオ・モンテヴェルディの『Cor mio, non mori? E morii』等を演奏。教会に氷のような澄んだ音色が響きわたりました。なお、カディッシュはロンドンの製作家フィリップ・イーレの楽器を使用しています。
多重録音に近い演奏スタイルについては、「自分の表現したい音楽を考えたら、自然とこの手法にたどり着いた」のだと語ります。電子音楽やポップス、ジャズなどにも普段から親しむ若いヴァイオリニストにとってはごく自然なことだったようです。
一方、土曜夜のコンサートでは、フィンランドにルーツを持つヨナタン・ローゼマン(チェロ)とラウリ・ポッラ(ベースギター)が登場。チェリストの聖典であるJ・S・バッハの無伴奏チェロ組曲を『再イメージ』し、大胆にアレンジした演奏を披露しました。
演奏が始まる前から、ホールにはフィンランドの自然の音、鳥のさえずり、舞台の大きなスクリーンに木や水などの写真が映し出され、森の中のような雰囲気が漂っていました。演奏が始まると、チェロが普段通りに無伴奏チェロ組曲を弾き始めてから、突然ジャズにつながったり、ロック音楽風になったりと変幻自在で、次は何が出てくるのかと目が離せません。
ベースギターの音にはノイズを混ぜてあったり、ディレイが強くかかっていたりとテクニックを駆使して響きを鮮やかに変化させており、チェロの切れの良い演奏と相まって、比較的年齢層の低い観客を集め、熱狂させました。

- 演劇と演奏が一体化した音楽劇『ガリレオ』
11日土曜の夜には、ガリレオ・ガリレイをテーマにした音楽劇が披露され、多くの人が会場に集いました。
バロック・オーケストラの前に俳優が一人。興味深いのは、音楽家には演奏以外にも、演劇の一部としての役割が与えられている点でした。例を挙げると、ガリレオの父がリュートを演奏していたため、舞台上のリュート奏者が父親としてガリレオに話しかけられる場面があったり、ガリレオが当時圧倒的な権力を持っていた教会から、地動説について異端審問を受けて否定される場面では、ソプラノ・アルト・テノール・バスの歌手らが俳優を取り囲んで歌い、批判を表現するなどの演出が光っていました。
16世紀後半から17世紀にかけての音楽と当時を生きたガリレオの物語が密接に関わりを持ち、舞台上で同時に表現されることで、音楽の聴こえ方が変わってきます。音楽に込められた当時の人々の喜怒哀楽が具体的な例をもって伝わってくるからなのかもしれません。
音楽を通して社会に向き合う
音楽祭最終日の夜、ルネサンス音楽を専門とする合唱グループのスティーレ・アンティーコは、17世紀初頭イングランドで活躍した作曲家ジョン・ダウランドの曲に現代の詩を乗せて歌いました。詩人ピーター・オズワルドによる難民の思いを代弁した詩には、難民や社会的マイノリティの心の声を代弁するものでした。ウードの奏でるアラブなどの音楽と交互に演奏され、地元ロンドンの難民が集った少人数の合唱グループとも共演。熱狂のうちに幕を閉じました。バロック音楽を通して、社会的なテーマにも向き合う試みとして印象に残りました。

- これからのバロック音楽
同音楽祭芸術監督のケンプさんに改めてバロック音楽の持つ可能性について聞くと、このような答えが返ってきました。
「バロック音楽は17世紀初頭、感覚や感情をその場ですぐに端的に表現し、形にしたいという願望のうちに育ちました。ソロの歌に伴奏を付けるという形でのオペラはその発明の一つでした。バロック音楽は奏法として高低さまざまな文化に基づいており、即興を交えることが多く、主題にヴァリエーションを重ねていき、当時の人にとっての新しい楽器の色調豊かさや持ち味を味わうために用いられました。
今日のジャズ、ポップス、ワールドミュージックの音楽づくりと当時のものに違いはあるのでしょうか。確かな音楽家の手に渡れば、この共通点はスリリングな結果をもたらすことができるでしょう」
バロック音楽の技術や知識をふまえた上で、現代に生きる私たちにより近い音楽にも関わりながら、実験的な試みを続けている音楽家たちの演奏は刺激的です。今後、どのように発展してつづけていくのかが楽しみでなりません。
取材・文/安田真子
プロフィール:オランダ在住。音楽ライター、チェロ弾き
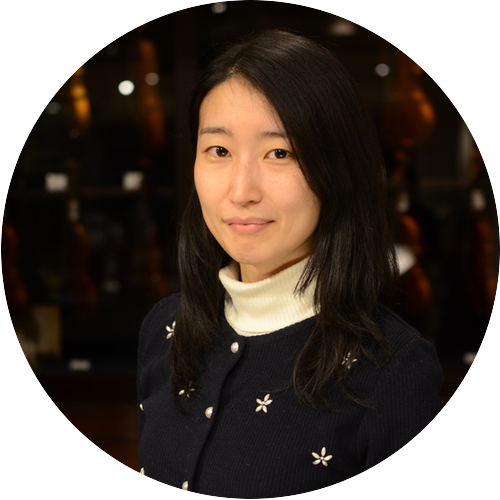
プロフィール:オランダ在住。音楽ライター、チェロ弾き