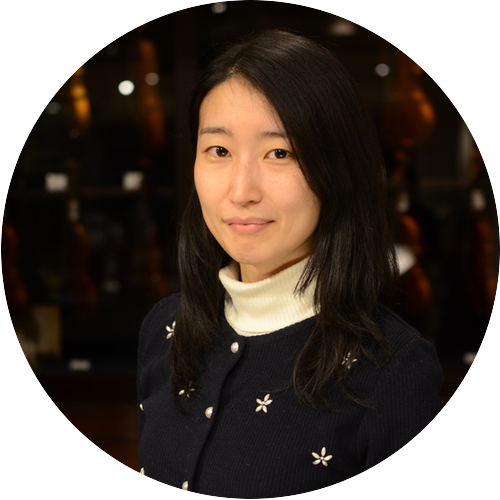■日曜・月曜定休
Closed on Sundays & Mondays
10:30~18:30
112-0002 東京都文京区小石川2-2-13 1F
1F 2-2-13 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 JAPAN
後楽園駅
丸の内線【4b出口】 南北線【8番出口】
KORAKUEN Station (M22, N11)
春日駅 三田線・大江戸線【6番出口】
KASUGA Station (E07)
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form
- 毛替え予約(PC & 携帯より)Reservation for Rehairing

第17回 コロナ後初のコンセルトヘボウでの演奏会 in Amsterdam
オランダではウイルスの影響で3月半ばからコンサートなどが軒並み中止になり、対人距離を1.5メートル確保することなどの措置が図られました。現在は、『対策が功を奏し、感染者数の抑制に成功している』というオランダ政府の判断のもと、措置が少しずつ緩和されつつあるという段階です。
6月からは最大30名、7月からは最大350名のイベントが開けるようになりましたが、まだ以前のような形式では催しが開けません。劇場やイベント主催者、音楽家などは、舞台芸術を聴衆に届ける方法を模索しつづけています。
今回は、コロナ後に初めてアムステルダムのコンセルトヘボウで開かれたコンサートについて、音楽家へのインタビューを交えてレポートします。
コンサートでのウイルス対策
6月12日、コンセルトヘボウの小ホールにて記念すべきコンサートが開かれました。コロナウイルスが発生してから関係者以外には門戸を閉ざしていたコンセルトヘボウで、初めて一般の聴衆を招き入れて行われた演奏会です。元々その日に演奏会を予定していたオランダ在住のチェンバロ奏者・天野乃里子さんは、開催に踏み切った背景についてこう語ります。
「基本的には30人しか聴衆の方々が入れないから、(演奏会は)全て中止という連絡がコンセルトヘボウ側から来ていました。そこで夫が急に『それはそれでいいではないか。30人でのコンサートをやったらどうか』と言い出して、コンセルトヘボウ側にも相談したら、是非ということになり、実行することになりました。ドリンクバーが開けられるか分からないから1時間のコンサートにしてほしいということで2回公演にするなど、コンセルトヘボウ側との手探りの決定条項が結構ありました」
実際に、約1時間の休憩なしの公演が夜7時と9時の2回に分けて開かれることになりました。事前に主催側から参加者へメールで連絡があり、政府のコロナ対策をふまえて対人間距離は常に1.5メートルを確保すること、建物に入る際は回転ドアを使って消毒液を使うこと、上着はクロークに預けずにホールに持って入ること、終演後はできるだけすぐに退館することなどの事項が知らされました。
当日、普段とは違う緊張感を覚えつつ、いつになく静かなコンセルトヘボウの建物へ入ると、目の前に消毒液の入ったポンプが待ち受けていたので、ここで手指を消毒しました。
受付を済ませて小ホールへの階段を上がると、意外なことにドリンクバーが開いていました。プラスチックの衝立越しに飲み物をオーダーして周りを見わたすと、距離をあけて配されたテーブルについて静かに過ごす人々の姿があり、すれ違う時にはお互いに近づきすぎないように、道を譲りあうようすも見られました。

微笑みを隠せない聴衆
小ホールの客席へ入る際には、スタッフから声をかけられました。「お好きな場所へどうぞ。ただし、他の人とは少なくとも3席空けて座ってください」
総座席数430名の小ホールにわずか30名なので、スペースにはかなり余裕がありました。
客席の電気が落ちてから周りを見わたすと、微笑みを隠し切れない人が何人も……! この日を心待ちにしてきた聴衆の胸の高鳴りが聴こえてくるようでした。
舞台に現れたのは、バロック・ヴァイオリン奏者の山縣さゆりさん、舞台中央にはチェンバロ奏者の天野さん。1.5メートル以内にいられるのは同一住所の家族だけというルールに則って、チェンバロの譜めくりを担当したのはヴァイオリンを演奏する12歳の天野さんのお嬢様でした。
冒頭の天野さんの挨拶の後、チェンバロ独奏で、ジャン=アンリ・ダングルベールの『シャンボニエール氏のトンボー』が演奏されました。
17世紀のフランスでは、作曲家の顧客である王や貴族が亡くなったとき、トンボー(追悼の器楽曲)という曲が捧げられることが多かったそうです。追悼曲であっても、この作品は明るく輝かしいニ長調で書かれており、亡くなった王の人生を讃え、天国に行ったことをイメージさせる追悼曲で、ウイルスの犠牲になった方々を思っての選曲でした。
その後、J・S・バッハの『ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ集』より3番、6番、6番の初期版のアダージョ、そして4番が続けて演奏されました。バロックヴァイオリンの豊かな響き、チェンバロのきらめくような音色が紡ぎ出す音楽に魅了されていると、1時間はあっという間です。演奏が終わると、観客の熱のこもった拍手が響き渡りました。スタンディングオベーションは禁止だったので、着席したまま拍手をしているうちに客電が点き、夢から覚めたような心地でした。
 後日、出演者のお二人にメール・インタビューでお話を伺いました。
後日、出演者のお二人にメール・インタビューでお話を伺いました。●演奏会が軒並み中止となってから、どのように過ごされていましたか。
「3月半ばは、18世紀オーケストラのリハーサルの真っ最中でした。明日から公演が始まろうとしている時に、7回の全ての演奏会がキャンセルとなり、オランダバッハ協会の毎年恒例の13回のマタイ受難曲もキャンセルとなり、20ものコンサートが、全く嘘のように消滅してしまいました。これから忙しくなるぞ、と身構えていたところだったので、この突然のフリータイムに頭が付いて行かず、呆然として最初の日々を過ごしました。
アムステルダムの音楽院でも、建物が封鎖され、レッスンや入試など全てがオンライン形式となり、手探りしながら過去に例のない方法で進められていきました。私が普段、よくレッスンですることは、楽器をどうすればよく響かすことが出来るかなどなので、オンラインレッスンでは、音自体を判断するのは難しく、私にとってあまり心地良いものではなかったです。
長年出来なかった片付けなどを、ぼちぼちやり始めてはみましたが、自分が何の役にも立つことが出来ないなと、結構気分が落ち込んでいました。それでも少しずつ状況に慣れて行き、何か新しいことでも始めようかと思いつつも、毎日があっという間に過ぎて、6月に入り観客30人の公演が解禁となり、この演奏会が3つ目です」(山縣さん)
「3月にはレクチャーコンサートがあって、その準備をしていたらキャンセルになり、4月の日本での私の後援会での総会コンサートもキャンセル、無論日本にも行かずでしたね。16歳と12歳の娘が2人おりますが、彼らの学校も自宅待機授業になり、家族揃っての通常ではありえない密接な時になりました。普段できなかった調べものなどができたり、それはそれで有意義な時であったかなとも思います。
世界的にも、この極小のウイルスが、人間たちがやめえなかった数種の内戦を停止させたり、現代の便利な生活に浸かっている我々の生活を再考察するきっかけにはなったと思います」(天野さん)
●2回に分けて公演を行うなど、以前とは異なる点がありましたが、演奏上ではどのような違いを感じられましたか。
「初めの予定では、BWV1014-1019の6曲全曲演奏の予定でしたので、2回同じプログラムで、3曲に減らし、1時間近く休憩もあったので、演奏すること自体はかえって楽でした。観客が少ないということに関しては、今までにも経験がありますし、少ないながらの雰囲気の良さみたいなものもあって、かえって良い演奏ができる場合もあります。ただ今回は、ストリーミングという未知の状況やラジオ録音等、目に見えない観客に一体どのように対応するか、気持ちの持って行き方は、少し難しかったです」(山縣さん)
「各コンサート30人という少ない人数だけれど、ライブコンサート再開に静かに興奮して、静かにその歓喜をシェアしてくださっているのが伝わり、この特別な機会に出席できたことを一生の宝にしたいなどの感想が寄せられ、こちらとしても嬉しく思っています。
ライブストリーミングやラジオの生中継、録音等で緊張した、ということは特に無いですが、同時に何万人もの人が今なお観て、聴けるというテクノロジーが存在する事実ってすごいなぁと感動しています」(天野さん)
●バロック音楽、特にJ・Sバッハの音楽は今の私たちに何を語りかけてくるのでしょうか。
「J・S・バッハの音楽は、バロック音楽というジャンルからかけ離れ、この人自身が、バッハというジャンルだと言っても良いぐらいだと思っています。いつどのような状況下にあっても、彼の音楽は変わることはなく、必ず人の心に沁み込み、癒してくれます。そんな音楽を、偶然とはいうものの、このような場面で演奏出来たことは、本当に相応しく、大変幸せなことだったと思います」(山縣さん)
「音楽の世界だけの話ではなく、ニュートンが万有引力の法則を発見したのと同様に、バッハも『美の法則』を発見したと言われ、カノンやフーガなどのバッハの作品は、彼の技術や能力が見出したものではなくて、すでに自然界に存在していた『美の原理』を音楽の形にして表したのだとも言われています。
このコロナウイルスの蔓延による未曾有の時期、人類の人知を超えたものを良くも悪くも体験したこの時期に、バッハ以外のプログラムは、逆にありえなかったと思います」(天野さん)

音楽は人類に必要不可欠なもの
今回の公演には、人類に欠かせないものとしての音楽を届けつづけるという強い思いが込められていました。「ドイツの文化大臣が、コロナ初期に『音楽は我々人類にとって必要不可欠なものだから、特にフリーの音楽家にちゃんと保障を出したい』と発表し、かなり早い時期に実行したように聞いておりましたが、オランダにはそのような保証は基本的にありません。それでも、隣国の文化大臣がそう発言されたこと自体、存在価値を問われている気がすると共に、大変に勇気づけられるものがありました。
本番中にもお話しましたが、これは単に我々二人のコンサートではなく、『音楽家たちの声』をお届けするということでありました」(天野さん)
天野さんが芸術監督を務めるシリーズ『バロックの真珠たち(Pearls in Baroque)』の一環として開かれたこの公演。11月19日にも同じホールでお二人の演奏会が予定されています。
「(同シリーズは)『バロックの音楽家達の活動の場を広げたい』という思いで始めましたが、古典派、ロマン派、又は、フランス印象派の音楽にもフレンチバロックのエッセンスが散りばめられていたりと、これは単にバロックだけのことに留まらず、大きな流れの中の基本なのです。
バロック、モダン(バロックの音楽家が普通のクラシックの音楽の世界を呼ぶ呼び方です)と分け隔てるのではなく、広く一般の聴衆の方たちにもお声をおかけしてオーセンティックな奏法で演奏していくことにご協力いただくとともに、それをシェアすることで一緒に深い喜びを得るという形を作っていきたいと思っています」(天野さん)
音楽を共有するための手段
昨今、ソーシャルディスタンシングという物理的な距離があり、多くの人と場所や空間を共有できない今だからこそ、人と人の心を近づける音楽の大切さが感じられます。今回の公演を通して、生演奏を聞くことは強烈で貴重な体験であることだと筆者は改めて感じました。それと同時に、より多くの人と感動を共有する手段の大切さを思い知らされました。その一例がストリーミング中継で、インターネット上の音楽配信は普及する一方ですが、実際に同じ空間にいられない分、発信者・受信者の双方が以前よりも積極的にコミュニケーションを取り、音楽に関わっていくことが必要とされているのかもしれません。多くの人とコンサートの空間を共有できる日が戻ってくることを祈りつつ、音楽がそこに存るということに深く感謝したくなる機会でした。
■コンサートの映像はこちら
https://youtu.be/N_HT1HlI3jM
写真 (c) Ronald Knapp
取材・文/安田真子
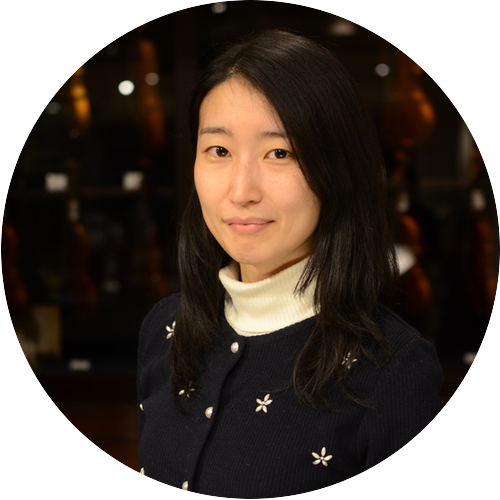
取材・文/安田真子