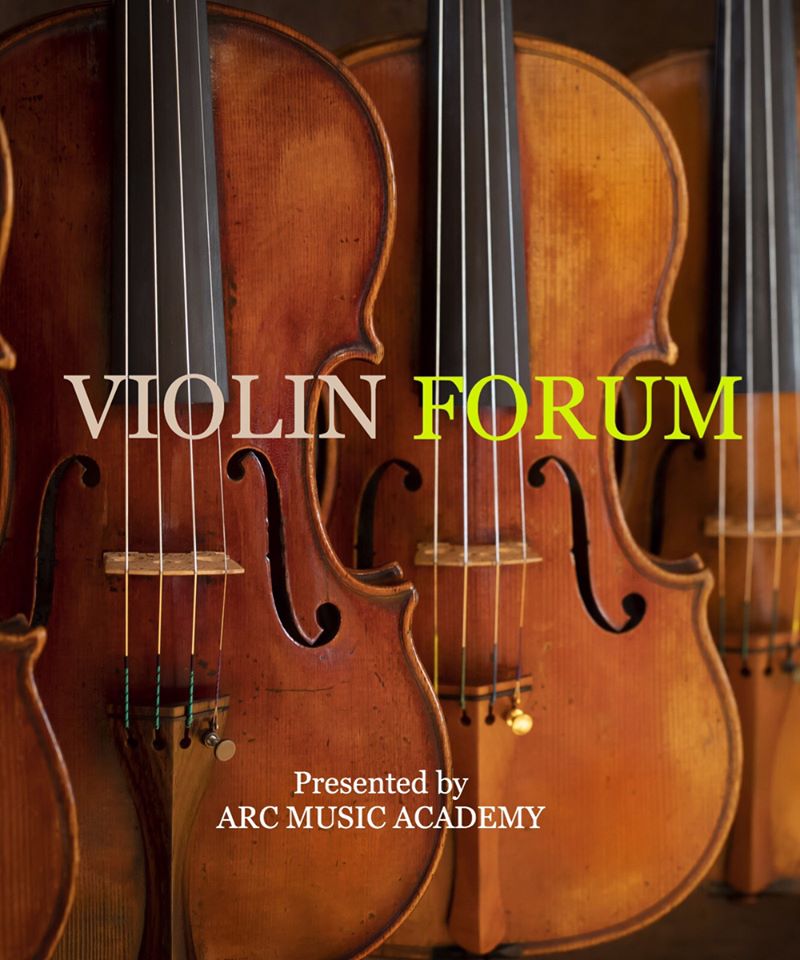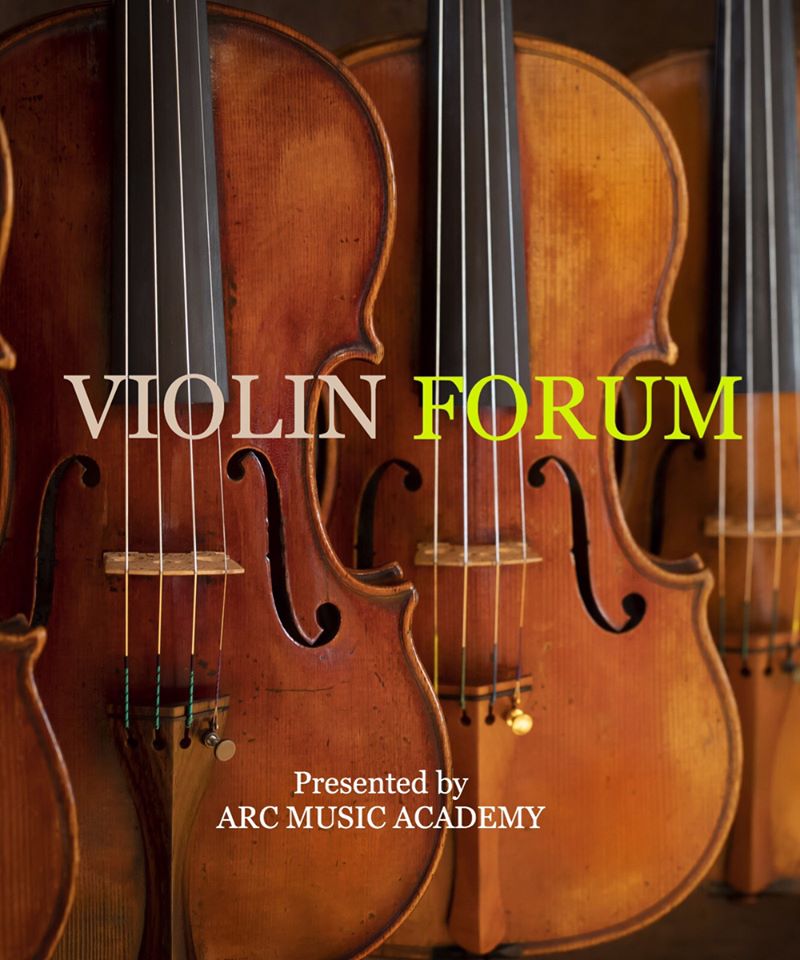■日曜・月曜定休
Closed on Sundays & Mondays
10:30~18:30
112-0002 東京都文京区小石川2-2-13 1F
1F 2-2-13 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 JAPAN
後楽園駅
丸の内線【4b出口】 南北線【8番出口】
KORAKUEN Station (M22, N11)
春日駅 三田線・大江戸線【6番出口】
KASUGA Station (E07)
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- 03-5803-6969+81 3 5803 6969
- お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form お問い合わせフォームInquiry Form
- 毛替え予約(PC & 携帯より)Reservation for Rehairing

-
Interview with Yoko Kubo

「ベートーヴェンを知るために、カルテットに取り組んでいるの!」
ジャパン・ストリング・クヮルテット(以下JSQ)の第一ヴァイオリン奏者、久保陽子先生は強い眼差しでこう話しました。チャイコフスキー国際コンクール第3位をはじめ数々の入賞歴をもち、バッハ、ベートーヴェンを中心に自身の音楽を追い求めてきた久保陽子氏に、楽壇生活のなかに占めるカルテット活動の意味するところを、JSQのこれまでを交えながらお話いただきました。
ーーまずはじめに、JSQでベートーヴェンを追い続けているわけを教えてください。
10代の頃からバッハとベートーヴェンが大好きで、そればかり弾いていたんです。他の作曲家はもういいやって(笑)。ただ20代になっても、どういうふうに弾けば良いのかがわからなかった。ヴァイオリンソナタの始めの一音でさえ、弾くのが難しかったんです。齋藤先生にしかるべき音楽のルールを教わる機会はあったけれど、全部を教わることができたわけではないし。
その不安はベートーヴェンを知らないからだと思ったんです。そこで、全ての作品を弾くところから始めたの。倉敷音楽祭で朝比奈さんの指揮でシンフォニー・チクルスに取り組みました。ヴァイオリン・ソナタも全10曲に取り組みました。そのあとに残ったのが多くのカルテット。知らないものを無くして不安を取り除くため、何より幼い頃から大好きだったベートーヴェンを極めたいという強い想いをもって、JSQでカルテット・チクルスに取り組むことにしたんです。弾けるものはとにかく全部弾いてみたかった。

ーーJSQ結成当時のことで印象に残っていることはありますか?
初めてJSQでカルテットの本番ステージに上がった時のことを良く覚えています。ベートーヴェンのファーストヴァイオリンなんて、難しくて絶対弾けないわって不安に思っている中、ステージ椅子に着席した対面に見えた菅沼さんは、それはもう岩のように堂々とした安定感で(笑)。この人はカルテットで音楽を積み上げてきた人なんだわって実感したんです。
ーー菅沼先生は昨年N響の首席でおられたときも、その存在感の大きさに圧倒されました笑。
そうなんです。なにかオーラというか、安心感がそこにあった。4人で練習するときも、わたしと岩崎さんは自分の思う音楽で突っ走りがちだったところを、菅沼さんが、ここは本来ならこうすべきだとか、海外の有名カルテットの誰それはこうしていただとか、四重奏曲の経験に富んだ意見でバランスを取ってくれていました。
ーー岩崎先生と久合田先生はどういう経緯でメンバーに加わったんでしょうか?
チェロの岩崎さんは中学高校のときから一緒に演奏してきた仲なんです。気心が知れていて、お互いの音楽に対する感じ方が似ていて、一緒に演奏するのに何の違和感もなく、同じ方向を向いていられた。これは長く続けられたポイントのひとつですね。
セカンドヴァイオリンの久合田さんはもともと「久合田緑弦楽四重奏団」のファーストヴァイオリンとして、長い間カルテットに取り組んでいたんです。このカルテットをやろうって2人で意気投合したとき、彼女がファーストヴァイオリンの目線から見てきた”セカンドヴァイオリンの理想像”を、このメンバーで実現したいって言ってくれたんです。
ーー本当にバランスの良い4人なんですね。20年以上続けることができるのも納得です。

ーー話は変わりますが、カルテットにおける難しさがあるとすれば、何でしょうか?
ソロとカルテットの違いで苦労したのは音程。ソロはオケの上に輝かしく鳴らすために、かなり張った音質で、かつ少し音程を高くします。その感覚をカルテットに持ち込まないようにすることが、特にラズモフスキー第1番の第1楽章で苦労した点です。また、各自の練習も最低限に必要ですが、4人集まってひとつの楽器ですから、4人の練習時間が必要であることも、物理的に難しさを感じています。
ーーソロとカルテットで、演奏に対するアプローチの仕方は変わります?
ソロもオケもカルテットも一緒の音楽。基本は変わらないと思います。ただ、ソロで背負う音楽への責任感が、カルテットの場合、少し分散するのかなと感じます。カルテットの場合はわたしも暗譜しませんしね(笑)。

ーー最後に久保先生が音楽に取り組むなかで、もっとも大切にされていることを教えてください。
自分の感性が一番大事だと、改めて感じています。人の意見を聞く耳を持ちながら、最終的に自分がどう感じるか、どう思うか、これを宝物にして音楽を表現したいと強く思います。
ベートーヴェンに対する大きな尊敬の念がJSQ20年の活動の原動力であり、それが今現在も続いている。その熱量を感じ取れるインタヴューでした。
3月11日(土)と12(日)には文京楽器小石川店舗にて、両日30名限定のサロンコンサートが開催されます。JSQのベートーヴェンを聴きに、是非とも足を運んでいただきたいと思います。